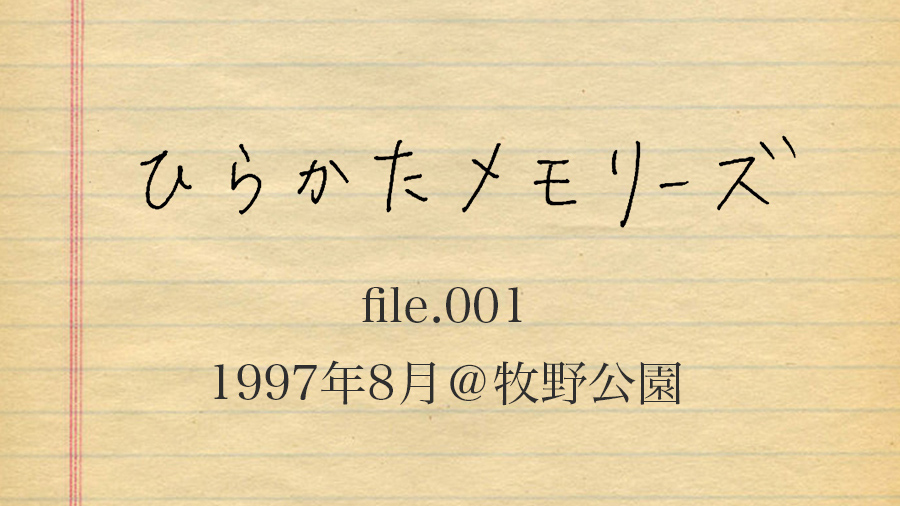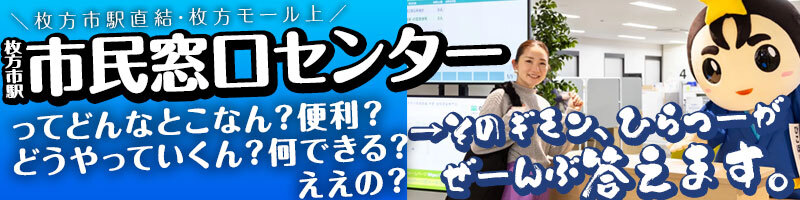1997年8月@牧野公園 夕刻
牧野公園はセミの声に包まれている。
いくつか並ぶベンチには、溶けたロウや黒く焦げた花火のあとが残る。その中で、もっとも被害の少ないベンチに腰掛けるのは高校生の裕介と由紀だ。日陰になるかどうかよりもベンチのキレイさで座る所を選んだせいで、まだまだ沈みきる気配のない太陽は二人を斜めから照らす。
肌からはじわりと汗がにじむ。
見るからに日に焼けた裕介は家族旅行から帰ったばかりだ。色白の由紀は早くも少し皮膚が赤らんできている。隣には裕介に渡されたお土産が並ぶ。
ヒゲを生やした船乗りがビットに片足をのせてたたずむ木彫りの置物。その土台部分には“Hawaii”の文字が彫られている。気に入ってもらえる自信のあったお土産のリアクションは薄く、不評であることは間違いなかった。イケてると思っていただけに、少なからずのショックを裕介は引きずったままだ。
二人の会話が途切れて数十分が過ぎた。小型犬を連れたおじいさんが通ったくらいで、園内には二人だけの時間が続いている。胸の部分にシャレた写真がプリントされた白いTシャツにジーンズの裕介。由紀はタイトパンツに淡いピンクのTシャツ。肩まで伸ばした髪が姿勢を直すたびに小刻みに揺れる。
裕介が黙り込んでしまった理由はお土産の失敗だけではない。彼は告白をするつもりで彼女を呼び出していた。
由紀は親友の彼女の友だちで、春からそのカップルを中心にグループで遊ぶようになった。外見は好みのタイプだったが一目惚れした訳ではない。由紀は覚えていないかもしれないが強く意識するようになったキッカケがあった。
ある日、別々のグループで話していた裕介は突然、由紀に呼びかけられた。振り向くとそこには裕介の顔を真正面から見つめる由紀の顔があった。直視する由紀と目が合い、裕介は固まった。それはほんの数秒のことだったのかもしれないが、裕介にとっては息の詰まる長い長い数秒間だった。次の瞬間、由紀はひょいとグループの方に向き直って言った。
「スケさんも左右で顔、歪んでるで~」
裕介はあっ気にとられた。
聞くと、由紀は左右の顔がだいぶズレていると友だちにイジられていたらしく“歪み仲間”を探していたのだ。ずいぶん失礼ともとれるこの振る舞いも彼にとっては別の意味を持つことになる。
無言で見つめあう二人
しかもあだ名で呼んでくれた
思春期の健全な男子高校生らしく、裕介は由紀のことが好きになった。
ハワイに行く前、みんなで花火をした。
少し遠出してみようというノリで京阪電車に乗って出かけたのだが、デタラメに降りた駅での土地勘は当然なく、なかなか適当な場所を見つけられない。両手に山ほどの花火を持って汗をかきながら歩き回るのも限界に達しかけた時、神社の横に広い駐車場を見つけたので、そこを拝借することにした。
片隅で円になって手持ち花火をした。由紀は逆さまに花火を持って火をつけようとしたりとおっちょこちょいだったが、それさえ裕介の恋心をくすぐった。打ち上げ花火の類いは結局できずに帰りも大荷物だったが、淡いひと時のあとの帰り道は苦にならなかった。
園内に残る花火のあとを見て思い出す。
それはほんの一週間ほど前のことだ。
裕介はベンチから立ち上がり、心を落ち着けるために公園を歩いてみることにした。告白に失敗するのが怖かった訳ではない。…まあ少しはそれもあったが、彼の中で勝算は五分五分、よりもちょっとプラス。
ただ根拠はなかった。由紀とはグループでは何度か遊んでいたが、そこでとりわけ仲良くなっていたわけでもない。“歪み仲間事件”が唯一の大接近だった。
アスレチックに登ってみる。
カラカラに乾いた木を踏みしめて、少し高い位置からベンチの由紀の様子をうかがう。由紀はうつむいて伸ばした足で地面に何かを書いては消していた。裕介の視線を感じたのか由紀がこちらを向くそぶりをみせたのでさっと身をひるがえし背を向ける。
夏の夕暮れは二人のことなどまるで相手にせず、沈むことすら忘れてしまったかのようだ。裕介の時間感覚も完全に失われていた。
友だちとブルーハーツのコピーバンドをやっている裕介にとっては、好きになったから告白するというストレートな流れはロックだった。勝算なんて関係ねぇ!好きだからその気持ちを伝える!セリフもストレートなものにすると決めている。
―好きです。付き合ってください。
これでいい。これがいい。
その一言を伝えるためロックな気持ちで呼び出したはずなのに、アスレチックの上のヘタレ男はコソコソ彼女の様子をうかがうだけだ。
今日はもういいか
今日じゃないのかもしれん
裕介はそういうことにしてベンチに戻った。うつむいている由紀の隣に座ると、すだれのように垂れた髪ごしに待ちくたびれた横顔がのぞいた。途端、気持ちは一転した。
これだけ待たせて言わんのはアカン!
止まっていた時間が思い出したように流れ始める。それに呼応するかのように裕介の鼓動もテンポを上げた。
のどにつかえた言葉で呼吸が苦しい。
うまく息を吸うことができない。
胸が苦しい。
でも、このままはもっと苦しい。
何度も生唾を飲み込んで、
そうしてそうして、
そうしてやっと、言葉が出た。
「あのさ…
好きです。付き合ってください」
裕介の鼓動のテンポは最高潮に達した。からだ全体が心臓になったように脈打つ。
それほど間を置かず、由紀は答えた。
「スケさんが悪いとかじゃないんやけど…
今は付き合うとか考えられへんねん」
「そっか…。わかった」
会話の流れは滑らかだった。
最大限に配慮した断りの言葉。
そっちか。そっちやったか。
半々の確率。コインの裏表。
裕介は妙に納得してしまった。
電池が切れたかのように脈動は感じられなくなった。というより、もう、そんなことを感じる心はどこかへ行ってしまった。
自転車で来ていた二人は、府道17号線を招提の方へ向かい前後になって走った。裕介の心は台風一過の青空のような、抜けるような空白だった。コノミヤを過ぎた辺りで二人の帰り道は別れる。自転車を止め、裕介は由紀の方を振り向いた。何を話せば…と、この間の花火が大量に余っていたことを思い出した。
「花火余ってるし、また花火しよな」
もうしないだろうな
そう思いながらも、裕介は言った。
「うん。またみんなで」
由紀も同じ気持ちだろうな
裕介はその声を聞きながら思った。
その夏、花火をすることはなく、大量の余りは裕介の部屋の隅で音もなく湿気た。