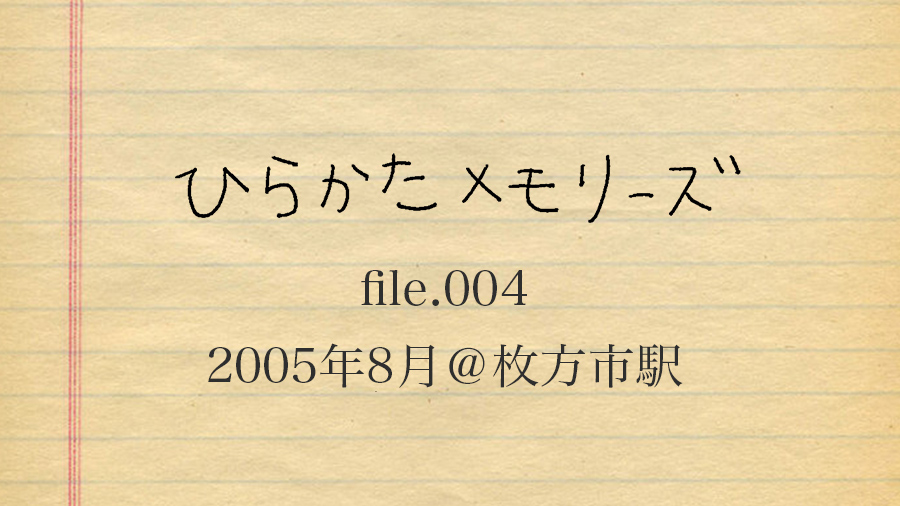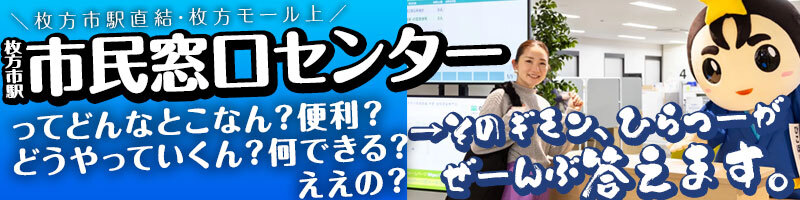枚方の人々の思い出を元にした、ほぼノンフィクションの読み切りエピソード集「ひらかたメモリーズ」、第4回をお届けします。
ひらかたメモリーズ file.004
2005年8月@枚方市駅 午後7時半
卒業以来に会う人ばかりで戸惑ったのは最初だけで、まだ開始30分を過ぎたところなのにテーブルは大盛り上がりだ。琴美はついついお酒がすすみ、周りの旧友もそれを後押しするかのようにメニューを広げておかわりを促してくれる。二杯目のグラスはすぐに届いた。
とそこへJがジョッキ片手にやってきて琴美の隣の狭いスペースに滑り込んだ。皆も何事かと一瞬声のトーンが下がったがJが腰を下ろすのが合図だったかのように会話は勢いよく再開される。
「琴美ちゃん、久しぶり!」
「あ、うん。…久しぶり」
「飲んでる? 何杯目?」
「まぁボチボチ。二杯目…かな」
「まだまだやん。どんどん飲みやー!」
赤ら顔のJはニコニコしながら琴美の肩に手を置いた。ぽんぽんと肩を叩くJの手のひらは大きくて少し柔らかい。確かに昔に比べて少し太った印象はある。女子からの人気もあった小学校時代から比べると劣化した感は否めないが、それは琴美も言える立場ではない。お互いに歳をとったし、琴美も琴美で色々あった。
「今、なにしてんの?」
「…Jくんは?」
琴美は質問に質問で返す。
「オレ? オレはさぁー…
そうやって語るJは、ちょっとチャラくなっていて、やたらとスキンシップをはかってきて、肩に置いていた手が背中にいったりもして、それでもそれがそれほど嫌ではなく、むしろ少し嬉しかったのはJが琴美の初恋の人だからなのであって…
…って感じよ。まぁ、頑張るしかないねんけどなー」
意識は体に触れ続ける手のひらに集中し完全に会話を聞き逃していた琴美は、思い出したかのように曖昧に相づちを打った。Jは残りのビールを一気にあおり店員を大声で呼んだ。
「琴美ちゃん、おかわりは?」
琴美のグラスは半分以上残っている。
「ほら、ついでやから頼んどき」
そう言ってJは少し雑にメニューをとって琴美に渡した。それは少し強引な気もしたがJの積極性が不快な訳ではないのだ。琴美は追加で同じものを頼むことにするとJが大声で自分のビールと琴美のおかわりを頼んでくれた。
テーブルではJと琴美にお構いなしで大笑いが続いている。
やっぱりちょっと強引で、ガサツ。
でも…イヤじゃない。むしろ…
むしろ、私は、嬉しいのだ。
あのときと一緒だ。
琴美は大切な記憶をたどる。
彼の隣で、彼と過ごした記憶を。
それは小学校2年生の時。彼は半袖を着ていたので夏頃だったと思う。
琴美はゲームが得意で、そのころは女の子よりも男の子と一緒に遊んでいた。その何人かのグループにJも居た。
ある日の帰り、琴美は彼に声をかけた。
「今日さ、ウチでゲームせえへん?」
「うん。ええよ」
なぜ彼だけに声をかけたのか覚えていない。後にも先にも二人っきりで遊んだのはその日だけだ。単純にゲームする相手が欲しかったのか、二人っきりになりたかったのか…そのあたりの記憶はひどくぼんやりとしている。学校から帰ると、急いでゲーム機をリビングに用意して彼が来るのをそわそわしながら待った。しかし、しばらくすると窓を叩き付けるような大粒の雨が降り出した。
強いにわか雨だった。
―こんな大雨じゃ来ないかもしれないなぁ
そう思いながら窓ガラスに勢いよく無数の透明な線を描く雨水を見つめた。
しばらく続いた大雨が小降りになってきた頃にインターホンが鳴った。琴美は驚き急いで玄関まで駆けて行きドアを開けた。そこにはずぶ濡れのJが(まいったなぁ)といった表情を浮かべながら苦笑いをしていた。琴美は急いで洗面所に向かいバスタオルを二枚つかんで玄関に舞い戻った。Jに一枚を頭からかぶせて、自分はもう一枚のタオルでJを拭いてあげた。
―彼が今、私の手の中にいるんだ
そう思うと嬉しいやら緊張するやらで心臓が張り裂けそうだった。Jは頭をゴシゴシ拭きながら、体は琴美に拭かれるままだった。
そのあとタオルケットにくるまったJと二人っきりでゲームをした。確か当時流行っていたレースゲームだったと思う。琴美の腕もなかなかのものでJとのレースは白熱した。
あの時琴美の独占欲は満たされていた。
大好きな彼が、私だけのものだった。
今も。しかもこんなに大勢のいる前で、Jの方から積極的に私の隣に座ってきてスキンシップまでして、飲み物のおかわりまで頼んでくれている。琴美は彼の話を上の空で聞きながら初恋の淡い記憶をたどっていた。
彼の手が肩から背中にうつり、そして、その手がゆっくりと腰の方まで降りていき、おしりの上まできた所で琴美はいきなり席を立った。
「ん?」
「あ、ゴメン。ちょっと…トイレ…」
琴美は彼の後ろを通ってトイレに向かった。彼の琴美を見上げる視線を感じたがそれには気づかないふりをした。このままでは変な方向に行く気がした。まだ一次会で、開始から一時間を過ぎたあたりでのこの感じは、やっぱり、ちょっと、マズい。トイレの個室の鍵を閉め、琴美は自分に言い聞かせた。
冷静になれ、冷静になれ、冷静になれ
いくらなんでも、まだ、早いぞ、と。
しばらく時間を置いて席に戻るとJは移動していた。ホッとしたような、でもやっぱり残念な気がした。そこからはみんなの輪に加わり昔話に花を咲かせながら大笑いをした。二人だけの濃密な時間はまるでなかったことのようにJはみんなの中に紛れ、琴美も笑いの中に紛れた。さっきまでのことは夢だったのかもしれない。酔いが回るにつれ琴美はそんな気が無性にした。
大盛り上がりのなか一次会はお開きになり、ほぼそのままの人数で二次会のカラオケへ移動することになった。
いい気分で歩いている琴美の腕を女友達が引っ張って顔を寄せてきた。何事かと琴美は耳を近づけた。
いい気分で歩いている琴美の腕を女友達が引っ張って顔を寄せてきた。何事かと琴美は耳を近づけた。
「Jくん、彼女いるみたいよ」
「え?」
琴美の酔いは一気に冷めた。
彼女いるんだ。
それなのに、あんなことするんだ。
嬉しがってた私は…
馬鹿みたいじゃないか。
カラオケボックスでは狭い部屋に詰め込まれる形になったが、それが逆に楽しかった。琴美は曇った気持ちを晴らすためマイクを掴んで熱唱した。その様子に大盛り上がりする旧友たち。嬉しかったし、単純に楽しかった。
帰る頃には琴美は前向きな気持ちになっていた。彼は彼で幸せになればいいし、私も私で幸せになればいい。それでいいじゃないか。
琴美は少し上を向いて、歩いて帰った。
(おわり)
※冒頭の題字「ひらかたメモリーズ」は毎回ご本人に書いて頂いています。