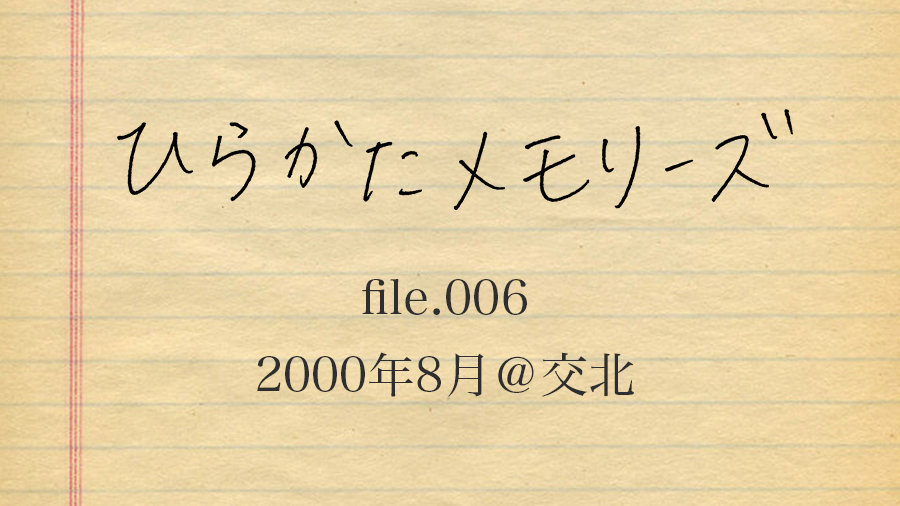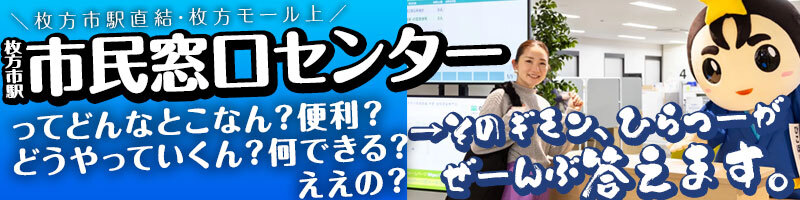ひらかたメモリーズ file.006
2000年8月@交北
悪気があったワケではなかった。
ただ、話していると楽しい。
それだけだった。
それだけだった。
だから、まさか、こんな風になるとは思っていなかった。
悠子と彼は、ちょうど一年前の夏祭りで初めてちゃんと話した。
悠子は彼に片想いをしていた。何人かのグループで夏祭りに行ったその中に彼は居た。時間が経つに連れてバラバラになり、気がつけば悠子は彼と二人で体育館の前に座っていた。
最初は他愛もない話をしていたと思う。
でも、途中から彼が、
「最近好きな子いるらしいけど誰なん?
教えてや」と聞いてきた。
教えてや」と聞いてきた。
広告の後にも続きます
「まぁまぁ…」
悠子はドキドキしながらごまかした。まさか好きな人からこんなことを聞かれるとは。でもこれはある意味チャンスなのかもしれない。
「何部なん?」
彼はひるまずに聞いてきた。それは純粋な興味といった感じだった。聞かずにはいられないというような。悠子は告白してもいいと思っていた。だから、正直に彼の部活を言った。彼は自分のクラブの名前が挙がるとは思っていなかったようでテンションが二段飛ばしくらいに上がった。
広告の後にも続きます
「え! 誰なん? ◯◯?」
「違う」
「△△?」
「違う」
「□□?」
「違う」
「じゃあ…◎◎?」
「…違う」
鈍感な彼はまさか自分が…と思っていたのだろう。こんな調子で最後に残ったのは彼だった。
「え?」
「うん」
広告の後にも続きます
悠子はコクリとうなずいた。暗闇の中でも彼の顔が上気するのがわかった。周りの空気が華やいだように見えた。
「アンタも好きな子いるって聞いたけど…
…誰なん?」
…誰なん?」
悠子は同じように質問責めに回った。
こちとら告白した身なので怖いものはない。悠子のテンションを抑えろという方が無茶だ。同じように部活から始まり、選択肢を消して行く作業が始まった。彼が好きな子が自分であったらいいなと思いつつ、でも、やっぱり「私のことが好きなん?」とは聞けなかった。
同じように最後に悠子だけが残った。
「うん。自分やで」
彼は照れながら言った。
二人は顔を見合わせてはにかんだ。夏祭りの盛り上がりはピークを迎えていた。
めでたく付き合い始めた二人だったが、付き合うということがどういうことなのか分からなかった。周りの付き合っている子たちは一緒に帰っていたので、そうするものだろうとは思ったが、悠子は恥ずかしくてそれすらままならなかった。
学校が早く終わる水曜日、彼から「一緒に帰ろうや」と誘われても「もうちょいみんな帰ってからにしよう」と言って、校舎が空になるまで教室で時間をつぶしたりしていた。彼の友達に茶化されるのもイヤだったから。
帰りは田んぼのあぜ道を通って帰るのでとにかく目立った。一緒に帰っているのに道の端っこと端っこらへんで歩いた。もちろん手なんてつなげなかった。それでも部活終わりなどは待ち合わせてたまに一緒に帰ったりしていた。
周りの友達も付き合い出し「手をつないだ」などの話を聞くと悠子は単純にうらやましかった。彼と手をつなぎたいな。でも自分から手をつなぎにいくのは恥ずかしいし…
そうして半年が過ぎた。
手をつないで帰るようになったのはその頃からだった。彼からつないでくれたと思う。でも悠子は手をつないでいるところを誰かに見られたくなかった。なのであぜ道を抜けて住宅街に入ったところから手をつなぐという暗黙のルールが出来上がった。その場所へ向かう道はいつもドキドキした。
あぜ道が終わりはじめの角を曲がると、彼は手をつないできた。悠子は恥ずかしながらもそれに応じた。それだけで充分すぎるくらい幸せだった。いつものように二人が手をつないで歩いていると、前から幼稚園児たちが勢いよく走って来た。走ることに無我夢中といった感じで、悠子と彼の間をすり抜けようとまっすぐに向かってくる。悠子は手を離そうと力をゆるめた瞬間、彼は悠子の手を強く握りしめて真上にあげた。園児たちは悠子と彼がつくったアーチの下を全速力で駆け抜けて行った。
彼は悠子の方を見て笑った。
悠子も笑った。
彼はどちらかというと寡黙でシャイだったのでよくわからないことが多かった。だから悠子は彼の友達に電話で相談したりしていた。そうしているうちに、その彼の友達を好きになってしまった。もちろん彼のことが嫌いになった訳ではなかった。でも、その好き以上に彼の友達のことが好きになってしまった。
彼にも悠子のその様子は伝わったらしい。
「アイツとあんましゃべって欲しくない」
そう言われた時、悠子はわかったフリをした。でも、気になる気持ちは抑えられなかった。
夏祭りの前に「別れよう」と言われた。
彼の友達とその後も仲良くしたことが原因だった。
悠子は「嫌だ」と泣いた。
彼の友達のことが好きになっていたけど、彼のことも好きだった。
わがままだとはわかっていたけど別れたくなかった。
そして今日の夏祭り。初めて彼と話してからちょうど一年が過ぎていた。そこには彼も、悠子が気になっている彼の友人も来ていた。悠子は彼をほったらかしにして彼の友人と話をした。
ただ、話していると楽しい。
それだけだった。
彼が「家まで送るわ」と言ってくれた時、悠子は咄嗟に「女友達と帰るからいい」と断っていた。なぜか送って欲しくなかった。どうせまた説教されると思ったのかもしれない。
家に帰り着くとすぐに電話が鳴った。
公衆電話からだった。
「もしもし…」
思い詰めたような彼の声がした。
「もう別れよ」
「わかった」
電話はそれで終わった。
長かった一年はひと言ずつの会話で幕を閉じた。
悠子は今でもあの道を歩くたびに彼と二人で作った腕のアーチを思い出す。
また音も立てずに、ひとつ夏が終わる。
(おわり)
・ひらかたメモリーズ一覧
・ひらかたメモリーズとは
広告の後にも続きます
※冒頭の題字「ひらかたメモリーズ」は毎回ご本人に書いて頂いています。